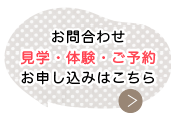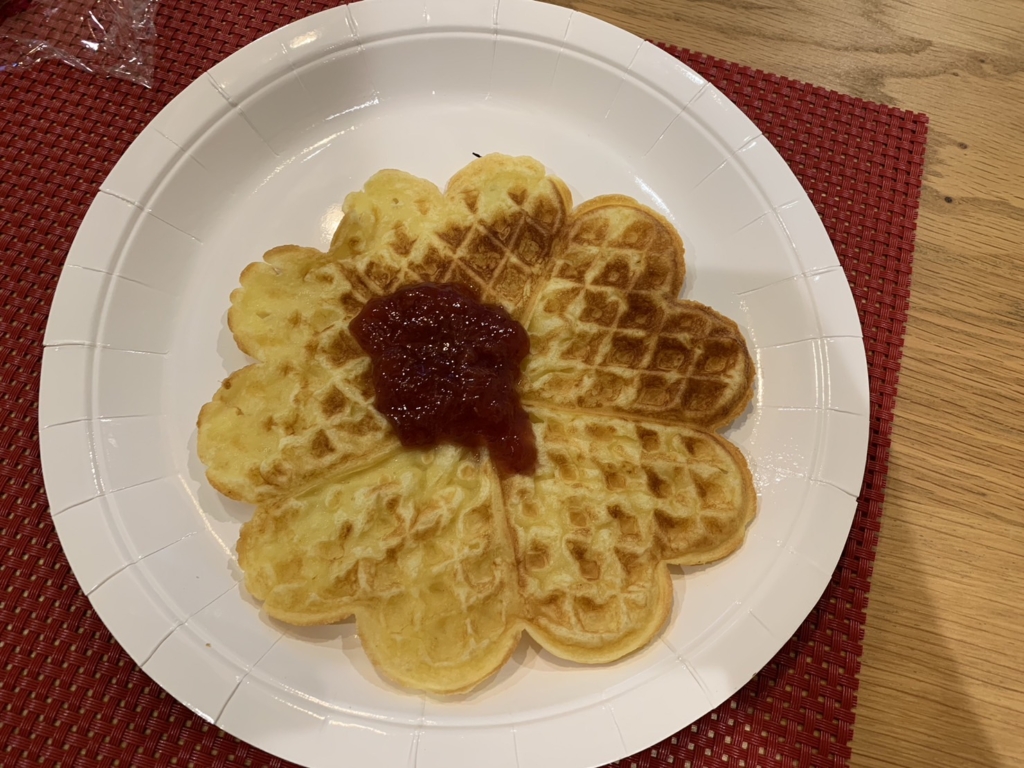7月30日の子供の部の発表会は「アリエッタ 夏のコンサート」としました。
生徒が順番に弾くという従来の発表会スタイルもいいのですが、発表会初めての生徒をいきなり弾かせるより、場を盛り上げるため、スタッフの友人たちと3人で6手連弾でオープニングスタート。

田邉英利子作曲
ハッピーカーニバル for 6 hands
Ⅰ長谷川薫
Ⅱ竹平智香子
Ⅲ田邉英利子
薫先生の発表会のために私が作曲、6手用にアレンジしました。6手連弾を初めて聴いた生徒は、すごかったーと言っていました。
ソロの部から3名紹介します。今年入会の生徒から中学生まで、12曲が演奏されました。今回、事前に演奏曲へのコメントを書いてもらい、演奏前に司会の薫先生に読んでもらいました。実は、みんな私の想像以上に、ちゃんと曲のことを考えて書いていたので、ビックリしましたし、成長しているんだ~、ととても嬉しかったです。

三善晃:海のゆりかご&久石譲:君をのせてを演奏したMさん
「海のゆりかご」の曲の、左手のフレーズがソで終わり、右手のメロディが同じソで始まるところの弾き分けを、Mさんは最初は苦労していましたが、ちゃんとできるようになりました。本人はこの曲はイルカが泳いでいるイメージとのことでした。自分なりのイメージを持つことはとても大切だと思います。連弾ではディズニーの「ちいさなせかい」のプリモパートを暗譜で演奏しました。

S姉妹は、フラジオレットを使ってピアノを響かせました。
フィンランドの教材から「うちゅう」という曲。妹のCさんは音が鳴らないように鍵盤を押さえると、姉の弾く音がペダルを使っていなくても響き出します。不思議な「うちゅう」の雰囲気が出ました。電子ピアノではできない面白さです。姉のWさんはほかにウェーバーの「人魚のうた」も演奏。とても仲の良い姉妹です。

RNさんは、前から弾きたかったサティの「ジムノペディ 第1番」を演奏。
この曲を始める時、右手のメロディ、左手のベース、そして和音…どういう順番ではっきり聴こえればいいか、質問したら彼はちゃんとわかっていました。ペダルを使って、堂々と演奏しました。
休憩後は連弾の部。
こちらも講師演奏からスタート。

グリーグ:抒情小品集より「妖精の踊り」の6手版(スレッシャー編曲)Ⅰ田邉英利子 Ⅱ長谷川薫 Ⅲ竹平智香子
連弾は、S姉妹プラス私で右手のみの3人3手連弾での「フレール・ジャック」ほか、全部で6曲の演奏でした。

K姉妹で日本の童謡「おうま」。妹のMさんは今年入会したばかりです。
Mさんは他にソロも3曲、両手で覚えるのも早かったです。連弾では姉のRさんがセコンドパートを担当。Rさんですが、ソロではドゥシェックのソナチネを力強く演奏しました。Rさんはいろいろな楽器ができて、すごいな~と思います。

RKさんはビリー・ジョエルの「ピアノ・マン」を連弾で演奏。
今回、一番シブイ曲はこの曲かも。本人が大好きな曲ということです。連弾はとても楽しいと言ってくれて、私も嬉しいです。ソロは田丸信明作曲「はずんだボール」、スタッカートの練習もがんばりました。

今回唯一のSさんの親子連弾。ジブリの「人生はメリーゴーランド」お仕事に育児に忙しいお母様ががんばってくれました。
この曲はテンポが変わる緩急があったり、#など臨時記号も多いですね。そして3拍子のワルツのリズムを合わせるのも難しいです。Sさんも、お母さんが一生懸命練習されている姿を見て、きっと励みになったと思います。Sさんはソロもジブリから、「あの夏へ」。他のレッスン曲より気合が入っていましたね。
そして
♪みんなで作った アリエッタ・キッズメロディー2023発表!
これは子供の生徒8人、1人2小節ずつで16小節の曲を完成させたものです。レッスンでは予め和声を決めていて鳴らし、生徒たちには即興的にメロディーをつけてもらい、繋がってから、強弱やアーティキュレーションをつけてまとめ、伴奏も弾きやすいようにしました。リハーサルの時にみんなに聴かせましたら、「いい!」という声も。本番を聞きに来てくれた友人も、面白いから楽譜がほしいと言ってくれました。自分の教室でもやってみるそうです。

まず、自分の作ったメロディのみ順番に演奏してもらい、あとから智香子先生に伴奏付きで演奏してもらいました。
他の先生からも、タイトルを募集したほうがいいんじゃない?と言われましたので、改めて募ろうと思います。入会まもない生徒もみんな、こういう力があるのです。楽譜通りに弾くことは大切ですが、それ以外の音楽の力もどんどん引き出していけたらと思います。
最後はソロ演奏。

田邉英利子編曲 わらべうた「あんたがたどこさ」
グリーグ 抒情小品集より「トロルハウゲンの婚礼の日」
「あんたがたどこさ」は手毬唄。毬付きは最近の子供はあまりしないと思いますが、最後にスカートの中で毬を留めるのですよね。今考えるとちょっと危険ですが、よくやっていました(笑)。曲のアレンジは、最後に毬を落としてコロコロ転がる表現をしてみました。2回目に成功して終わります。
グリーグの曲は、今回6手連弾と合わせて2曲、大人の部でもギターで演奏されましたが、今年はグリーグ生誕180年でもあり、講師演奏で選びました。そして私が永年勉強している作曲家でもあります。
とにかく、誰も欠けずに生徒たちが参加できたこと、親御さんたちの応援があったこと、スタッフのみなさん、とてもありがたく思います。
発表会後のレッスンで、「本番で間違えちゃった」と言ってきた生徒もいますが、「みんなが一生懸命練習してきたこと、ちゃんと弾けていたことは知ってるから、素敵なホールでみんなの前で最後まで弾けたことが立派なんだよ」と伝えました。それでもみんな満足していたようで、第一声に「楽しかったー!」と笑顔も5割増しだった生徒も。お友達のいろいろな演奏を聴いて、刺激になってくれればいいと思います。
また、聴きに来てくれた他の先生からも言われたのですが、うちの生徒たちは他の人の演奏もしっかり聴いていたし、お行儀もよいとのことでした。
ピアノだけではなく、何事もどこまでも勉強が必要ですが、今回のコンサートを省みて次にまた活かしていきたいと思います。